深浦マグロステーキ丼とは

「深浦マグロステーキ丼」の定義
マグロは大間だけじゃない!
「青森県のマグロ=大間のマグロ」というイメージが定着していますが、水揚げ高では深浦町が青森県ナンバーワン!ということで、深浦町産の天然本マグロを三個の小どんぶり(マグロ刺身丼、マグロ片面焼きステーキ丼、マグロ両面焼きステーキ丼)で楽しむ、天然本マグロの産地ならではのマグロ尽くしどんぶり御膳です。

マグロ刺身・マグロステーキ・野菜焼き
皿に盛ったマグロは、つまと共に王道の刺身で。
串刺しのマグロは串から外し、1本は片面を焼いてミディアムレアのねっとりした口当たりを、1本は両面焼きで香ばしさとしっかりした味わいを楽しんで。
季節の野菜焼の具材は各店オリジナル。

ジンギスカン鍋
すぐ焼けて、煙が出ず、油やバターを使わなくてもくっつかないと、いいことづくめ。焼く時のジュウジュウいう音も御馳走。

3種のタレ
刺身はわさび醤油(左)、片面焼きマグロステーキは全店共通の辛味噌(中)で。両面焼きステーキのタレ(右)は、各店が工夫をこらして創りあげたオリジナル。
醤油系、マヨネーズ系、酸味でさっぱり系…と、どれも甲乙つけがたく、全店制覇したくなる味わい。
各店舗のこだわりのタレを見る!

3種の丼
ベースはすべて白飯。深浦産長いも(ネバリスター)にわさびを薬味にした丼(左)には刺身、錦糸卵の丼(中)には片面焼きステーキ、マグロ節の丼(右)には両面焼きステーキを、それぞれのせていただくのがオススメ。すべての丼にあしらった国産海苔の香りもポイント。

季節の香の物
四季折々の旬の地場産食材を使ったお漬物にも各店のこだわりが。自家菜園でとれた野菜を使っている店も。

つるつるわかめを使った汁物
白神山地ブナの森から注ぐミネラル豊富な海で育った天然わかめ、麺タイプわかめを使用。各店オリジナルの味噌汁、お吸い物。

各店こだわりのデザート
カクテルグラスで提供される季節のデザート。深浦町特産の「雪にんじん」のペーストや、トマトなどが彩を添える。
「深浦マグロステーキ丼」のルール
- 正式名称は「深浦マグロステーキ丼」とする
- 愛称・略称は「マグステ丼」とし、キャラクターは「マグステ君」とする
- 青森県ナンバーワンの水揚げを誇る深浦町産の天然本マグロ(120グラム)を使用する
- マグロは、刺身用(40グラム、皿盛り)、片面焼きステーキ用(40グラム、鉄串刺し)、 両面焼きステーキ用(40グラム、鉄串刺し)に分ける
- 季節の野菜(なるべく地場産野菜)を使用する
- マグロと野菜は一人用ジンギスカン鍋で焼いてもらうマグロを焼く時は、鉄串からマグロを抜いてジンギスカン鍋にのせてもらう
- 青森県産(なるべく深浦町産)のお米を使用する
- 3つのごはん茶碗(それぞれ80グラム)に、それぞれマグロの刺身、マグロの片面焼きステーキ、マグロの両面焼きステーキをのせて、
小どんぶりとして食べてもらう
すなわち、「マグロ刺身丼」「マグロ片面焼きステーキ丼」「マグロ両面焼きステーキ丼」である - 「マグロ刺身丼」はわさび醤油で、「マグロ片面焼きステーキ丼」は 各店共通のタレ(毎年変更)で、「マグロ両面焼きステーキ丼」は各店オリジナルのタレ(毎年変更)で食べてもらう
- ごはんの上のトッピングは、協議会指定のものとする
- 深浦町の名産品「つるつるわかめ」を使った各店こだわりの汁ものをつける(「つるつるわかめ」以外も、なるべく、旬の地場産食材を使用する。料理内容は、季節等に応じて、自由に変えても良い)
- 各店こだわりの香の物をつける(なるべく、旬の地場産食材を使用する。料理内容は、季節等に応じて、自由に変えても良い)
- カクテルグラスに入れた各店こだわりのデザートをつける(なるべく、旬の地場産食材を使用する。料理内容は、季節等に応じて、自由に変えても良い)
- 協議会指定のジンギスカン鍋と五徳・3つのごはん茶碗(蓋付き)・マグロ&野菜皿・タレ皿・香の物皿・汁もの茶碗・デザート用カクテルグラス・オリジナルマグロ箸置き・お膳と各店自由の箸・スプーンを使用し、協議会指定のレイアウトにする
- 協議会指定の箸袋を使用する。
- 替え玉ならぬ「替えマグ」システムを導入する。マグロのお代わり(刺身用マグロ40グラムもしくはステーキ用串刺しマグロ40グラム)は、 それぞれ250円(税込)とする
- ごはんのお代わり(小どんぶり)は100円(税込)とする
- 料金は1800円(税込)以下とする

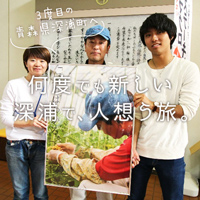

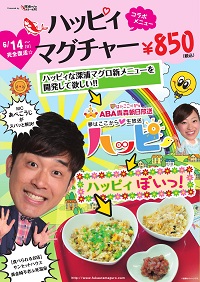







ヒロ中田
じゃらんリサーチセンター
空飛ぶご当地グルメ
プロデューサー
「新・ご当地グルメ」の提唱者&プロデューサーで、これまで約70の商品を誕生させた。
2015年10月26日、「深浦マグロステーキ丼」(深浦町の人口は9000人)は累計10万食を達成しました。デビュー後864日(約2年4か月)での快挙です。これまでぼくは70近い商品を手がけてきましたが、早さで言えば「オホーツク北見塩やきそば」(北見市の人口は12万1000人)に次いで全国2番目。北海道を代表する新・ご当地グルメ「富良野オムカレー」(富良野市の人口は2万3000人)より早いのですから、この出来事がいかにすごいかおわかりいただけることでしょう。
「深浦マグロステーキ丼」10万食の経済効果は5億5568万4844円、外貨獲得額は5億1123万0056円。陸の孤島・深浦町が、「深浦マグロステーキ丼」で息を吹き返したのだとしたら、プロデューサーとしては望外の幸せです。
「深浦マグロステーキ丼」大ヒットの要因は3つあります。ひとつ目は、商品名から受けるイメージを完全に裏切ったこと。誰も、刺身丼・片面焼きステーキ丼・両面焼きステーキ丼3種類のどんぶりを食べられると思わなかったにちがいありません。ふたつ目は、「マグロは大間だけじゃない!深浦町はマグロの水揚げ青森県ナンバーワン!」というメッセージが刺さったこと。これは強烈なインパクトがあったと思います。みっつ目は、西崎朋監督率いる「チーム深浦」の機動力。打ってよし、走ってよし、守ってよしの三拍子揃ったチーム力が、この大記録を打ち立てたのです。
「深浦マグロステーキ丼」に続いて、青森県内では「平内ホタテ活御膳」「中泊メバルの刺身と煮付け膳」がヒットし、2016年3月には「田子ガーリックステーキ膳」がデビューする予定になっています。まさに、「深浦マグロステーキ丼」が火付け役となり、県内各地で食による地域活性化がスタートしているのです。
深浦町には、素晴らしい風景(日本海に沈む夕陽、青池など)や人気の温泉(黄金崎不老ふ死温泉など)があります。<風景×温泉×食>で交流人口増加を図る深浦町の挑戦は、地方創生のモデルになっていくかもしれません。
青森県で新・ご当地グルメを開発することになったのは、ある地域バカとの出会いがあったからです。2011年11月2日、ぼくは青森県中小企業団体中央会さん主催の講演会で「食をテーマにした地域ブランドの創り方」と題して話をさせていただきました。対象は中小企業(民間)の方々だったのですが、なぜか公務員である深浦町役場の青年が紛れ込んでいたのです。もじゃもじゃで茶色の長髪。そう、後に県内で有名になる鈴木マグロー君です。
最近つくづくこう思っています。「食が地域を熱くする」の正しい表現は、「人(地域バカ)が地域を熱くする」のだと。 (談)